教員紹介
放送大学千葉学習センターに所属する客員教員、担当するミニゼミをご紹介します。(※令和7年10月1日現在)ミニゼミとは?
「ミニゼミ」は放送授業や面接授業と違い、少人数で教員を囲みながら、各教員の専門分野をテーマに、発表、討論、実験、観察、課外活動など様々な学習スタイルで行われています。年齢や性別も異なる学生のみなさんが、指導教員のもと、共通のテーマを学びながら毎回楽しく活動しています。興味のあるテーマを学ぶとともに、他の学生や教員と交流していただくことも目的としていますので、試験や成績判定といったことはありません。
2025年度10月期は10(2つは募集終了)のゼミで受講生を募集します。放送大学の学生であれば、どなたでも無料(一部ゼミは費用負担あり)で参加できます。受講生は随時募集しておりますので、ご興味のある方は、是非お申込みください。

潤間 励子(ウルマ レイコ)
『社会と感染症~スピンオフ~』
毎年、千葉学習センターで「社会と感染症」という面接授業を行っています。そこで、議論し尽くせなかったテーマについてミニゼミで討論したいと思います。
主には感染症が社会に与える影響とその対策について討論したいと考えています。かならずしも医学的な知識が必要ではなく、一般市民がどのように考えるのか?行動するのか?に焦点を当てていきたいと思います。
①話題提供 ②参加者による相互討論 ③次回のテーマ決め→自宅学習では次回テーマについて情報収集してください。 という手順で進めたいと考えています。
初回テーマは「COVID-19パンデミックを振り返る」とします。

伊藤 誠(イトウ マコト)
客員教授 / 専門分野:音楽科教育・ヴァイオリン
『ヴァイオリン・アンサンブルの楽しみ』
ヴァイオリンの構え方や正しい姿勢、楽器の手入れの仕方から始まり、音程づくりの初歩はピチカート奏法(指で弦を弾く方法)で進めます。左手の型が身に付いてきた時点で、弓(ボゥイング)を使って音を作っていきます。導入期の教材は「わらべうた」や「童謡」ですが、単に楽譜通りに演奏するだけでなく、簡単なアンサンブルの形態を取り入れながら、楽しく楽器に親しんで頂くことをねらいとしています。個別指導と集団学習を併用して進めます。他の受講生の練習を参観することも大切です。自分が属さないグループが参加する週に見学することは自由です。時間のゆとりがある方は予習・復習に役立てて下さい。
定員満了のため募集終了しました

三野 弘文(ミノ ヒロフミ)
客員教授 / 専門分野:物理学
『偏光色アートを楽しもう』
二枚の偏光板を透過軸を直交にして重ねると光が遮断されます。その間に透明なセロハンテープなどを挟むと、光が透過するようになり、枚数に応じて発色が変化します。
この現象は偏光色と呼ばれますが、この偏光色のしくみについて、物理学の視点から実測と数式を用いて学び、光と色の関係や偏光について理解いただいた上で、偏光色を使ったアート作品の制作なども行います。
偏光色予測シミュレーションも使用を予定しており、その際は、別途指示いたしますが、PCをご持参いただくことになります。
受講条件:受講条件としてノートPC(Windows)をご持参ください。
【用意するもの】①ご自分のパソコン(タブレット、スマホ不可)を用意することができること
②放送大学のWi-Fiに接続可能なこと(接続については学習センターのWEBサイトをご確認ください)

柴 佳世乃(シバ カヨノ)
客員教授 / 専門分野:中世文学
『私の推しの古典文学』
古典文学には、古くて新しいいろいろな要素が詰まっています。日本の古典文学の中で(どの時代でも結構)、自分が興味を持っている/気になる/これから読んでみたい作品を各自取り上げ、その特徴や面白さに ついて、自由に発表してもらい、皆で議論します。自分の〈推し〉の古典文学の特徴を再発見するとともに、 たくさんの作品に触れることで、多様な古典文学の面白さを皆で共有したいと思います。

矢口 貴志(ヤグチ タカシ)
客員准教授 / 専門分野:真菌学
『生活環境中のカビ』
月1回、講義のあと討論するセミナー、残りの時間は、それぞれが自由に観察、実験など行う。現在、予定しているテーマは以下の通りである。
1.真菌の分類体系 2.Aspergillusの分類 3.Penicilliumの分類 4.室内環境のカビ 5.内臓真菌症原因菌
6.皮膚真菌症原因菌 7.カビ毒 8.カビが産生する有用物質 9.耐熱性カビ 10.マイセトーマ(皮膚病)の検出
(ゼミは教室での対面を原則としますが、ZOOMを利用した遠隔での参加も可能です。)

高橋 浩之(タカハシ ヒロユキ)
千葉学習センター所長・特任教授 / 専門分野:健康教育学
『保健の授業を学び直す』
皆さんの多くは「保健」を中学・高校で受けた退屈な授業と考えているでしょう。しかし、実際には、新たな感染症から最新のがん治療、性についての自己決定から高齢者の健康、心肺蘇生法から医者のかかり方など、面白い上に人生の基盤になる内容を保健は扱っているのです。このゼミでは、高校の教科書を題材にその背景やさらに深い知識、また、発展的な内容に関してみんなで学んでいきます。

御巫 由紀(ミカナギ ユキ)
客員教授 / 専門分野:植物分類学
『薔薇学講座』
園芸植物として長い歴史を持つバラについて、植物学、歴史、美術等あらゆる面から、バラの魅力を解説する。バラは西洋文化の象徴のように思われているが、約200年前にアジアのバラがヨーロッパに運ばれ、育種に用いられて初めて現代の栽培バラが誕生した。日本に16種類ある野ばらの見分け方、バラの育種において日本の野ばらが果たした役割、オールドローズとモダンローズの系統、日本のバラの歴史等について、教室での講義とバラ園の見学を合わせたゼミを行う。
(ゼミは教室での対面を原則としますが、ZOOMを利用した遠隔での参加も可能です。)

伊藤 愼(イトウ マコト)
客員教授 / 専門分野:地球科学
『地層の縞模様から読み解く大地の成り立ちと地球環境変動史』
地層には様々な形、厚さ、長さ、高さなどを示す縞模様が観察されます。このような縞模様は「堆積構造」とよばれ、地層を構成する粒子が運搬され堆積するまでの一連のプロセスの特徴を記録しています。したがって、堆積構造の特徴から地層を形成した流れの種類、方向、速さや強さ、深さや厚さなどの特徴を解読することができます。さらに、堆積構造の特徴から、地層が形成された堆積環境の変遷やその要因を解読することもできます。このゼミでは、講義や文献の輪読、参加者のプレゼン,さらには室内実験や野外観察などをとおして、「堆積構造」の特徴と形成プロセスの理解を深めるとともに、堆積構造から読み取れる大地の成り立ちや太古から現在に至る地球環境変動史の理解を目指します。

片岡 洋子(カタオカ ヨウコ)
客員教授 / 専門分野:教育学
『ジェンダー・セクシュアリティについて考える』
ジェンダー・セクシュアリティについての世界と日本の課題について考えるため、関連した本を読んでいます。2025年度は5月から守如子・前川直哉編『基礎ゼミ ジェンダースタディーズ』(世界思想社 2025年 1900円税別)を読んで章ごとにレポーターを決めて進めています。本の購入が必要です。
*書名に注意!「メディアスタディーズ」ではなく「ジェンダースタディーズ」です。 2023年度は神谷悠一『差別は思いやりでは解決しない ジェンダーやLGBTQから考える』 (集英社新書2022年)、辻村みよ子『ポジティヴ・アクション』(岩波新書 2011年)、2024 年度は、三浦まり「さらば、男性政治』(岩波新書 2023年)、千葉勝美『同性婚と司法』(岩波新書 2024年)を読んできました。
(主にZoomを使ったオンライン開催です。)

八馬 智(ハチマ サトシ)
客員教授 / 専門分野:環境デザイン
『日常の風景を読み解く』
身の回りの風景をじっくり眺めてみると、それまで見過ごしてきたさまざまな要素によって構成されていることに気がつきます。それらを手がかりにしながら、「観察」「考察」「洞察」を繰り返し行うことで、視野が拡張され、視界の解像度が高まり、自分なりの風景を再発見することができます。その体験は、地域や社会に内在する「文化」への深い理解に結びつきます。このゼミでは、受講生自身による「まち歩き」の実践を通じて、自分の中にある「面白い」という感情を呼び起こし、プレゼンテーションやディスカッションを通じた「言語化」を繰り返すことで、新たな価値を発見することを体験していただきます。

金子 智栄子(カネコ チエコ)
客員教授 / 専門分野:教育心理学・保育心理学
『子どもを理解し、子どもに学ぶ』
子どもは可愛いですが、それ以上に面白い存在です。特に年齢が低いほど見るものすべてが新鮮で、この世は発見に満ちています。よちよち歩きの赤ちゃんは、知的好奇心に満ち溢れたキラキラしたまなざしをもっています。そのようなまなざしを大人になっても持ち続けられたら、人生は幸せなことでしょう。乳幼児期の体験は、その後の発達にも大きな影響を与えます。そこで、乳幼児期からの子どもの発達について.共に学び、子どもの素晴らしさを共有したいと思っています。さらに受講生ご自身の発達についても、振り返る機会にしたいと思っています。
(ゼミは教室での対面を原則としますが、ZOOMを利用した遠隔での参加も可能です。)
定員満了のため募集終了しました
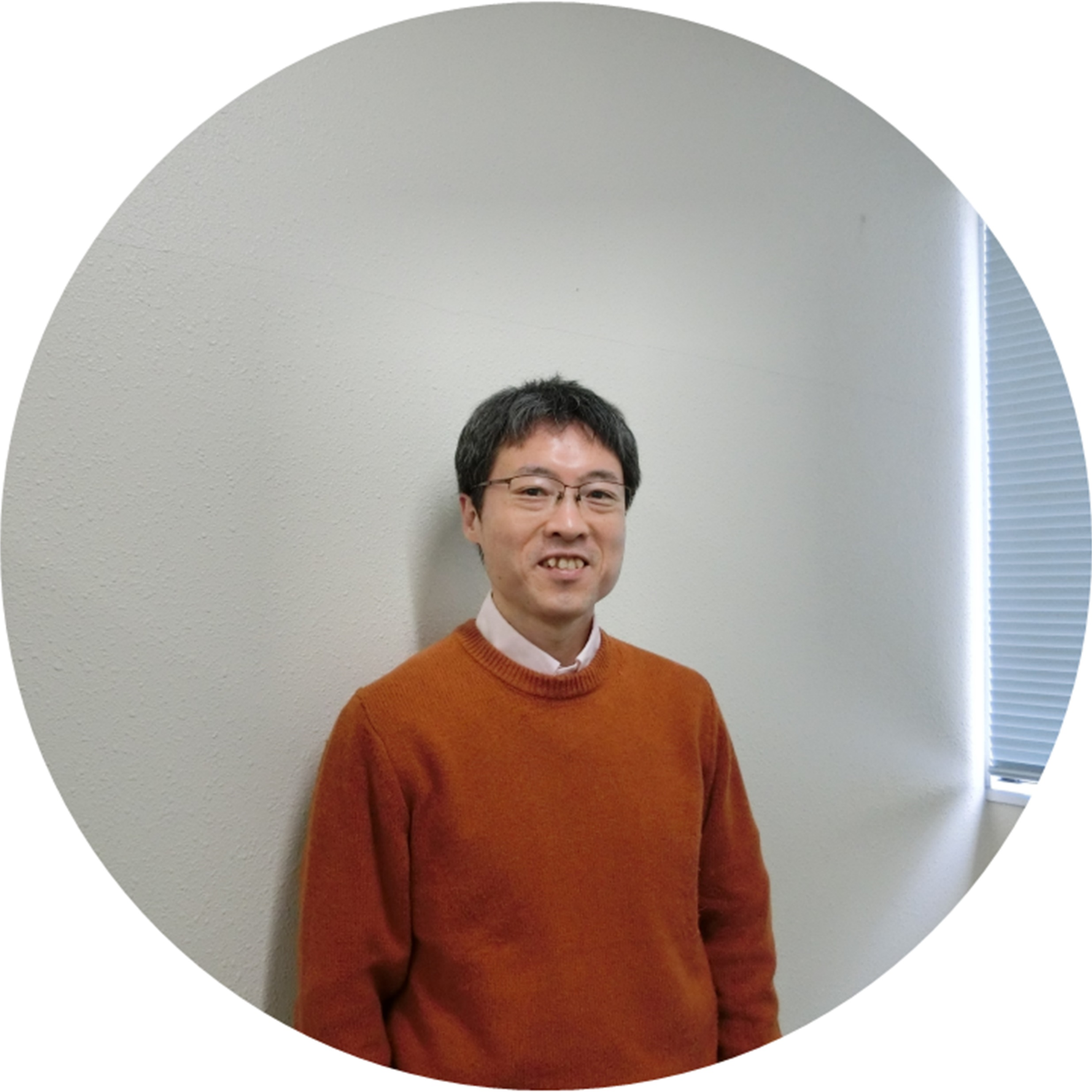
青砥 清一(アオト セイイチ)
客員教授 / 専門分野:スペイン法学・スペイン語
『スペイン語とスペイン・ラテンアメリカの文化』
前半の1時間は初級~中級レベルのスペイン語演習(文法、聴き取り、作文など)を行います。後半の1時間は、スペイン・ラテンアメリカの文化・歴史・社会に関するスペイン語文を読んだり、ゼミ生による研究発表を行ったりします。
(ゼミはZoomを利用したオンライン形式で実施します。)
定員満了のため募集終了しました


