教員紹介
栃木学習センターでは、所長をはじめ8名の客員教員がそれぞれの専門分野のほか、学習の進め方や卒業研究・レポートの作成など学習全般について個別に相談に応じています。お気軽にご相談ください。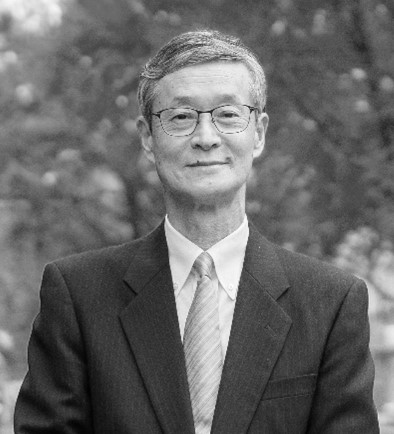
加藤 謙一
栃木学習センター所長/宇都宮大学名誉教授/専門分野:体育学(発育発達、陸上競技)
2006年から2011年度まで客員教員としてお世話になっておりました。この度、所長として勤務することになりました。どうぞよろしくお願いいたします。
就学前の子どもから高校生までの運動発達について研究してきました。体力テストのようなタイムや距離などの数値データに基づいた結果だけでなく、運動の仕方、例えば、走り方、跳び方、投げ方などがどのように向上していくのか、向上させるためにはどのような支援が必要なのかを明らかにしようとしてきました。現在の子どもたちの体力や健康の保持増進について一緒に考えていければと思います。
プロフィール:大阪生まれ、愛知県三河育ち。筑波大学大学院体育学研究科修士課程修了、1985年宇都宮大学教育学部に着任。2025年3月に宇都宮大学を退職。博士(体育科学)2004年。
面接授業科目:運動発達論(2007年・2012年)、子どもとスポーツ教育(2009年)
特別ゼミのテーマ:科学的な論文(報告書)の作成のためのデータのまとめ方(2007年・2010年・2011年)
艮 香織
客員教員/宇都宮大学准教授/専門分野:教育学・保健学
子どもから大人までの性の健康は基本的人権です。包括的性教育や人権教育はこれを保障するための重要な権利です。国内外の授業観察や教材分析を通して、学校や家庭、社会教育でどのような実践が可能なのかを研究しています。また、戦争孤児の戦後史について、児童養護施設等に残された史料や聞き書き調査から考察をしています。
プロフィール:専門は包括的性教育、人権教育、子ども家庭福祉。博士(保健学)
面接授業科目:「男女共同参画」と人権(2016年)、人権としての〈性〉を考え
る(2020年)
特別ゼミのテーマ:人間の一生と〈性〉を考える(2025年)
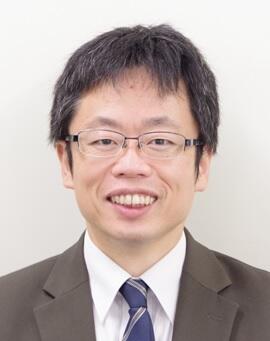
岡澤 慎一
客員教員 / 宇都宮大学教授 / 専門分野:特別支援教育・重複障害教育・教育心理学
障害のある子どもや成人の方と係わり合いをもたせていただきながら、教育のあり方やコミュニケーションの実際について、実践研究(Action Research)を重ねてきました。障害の有無を含め、様々な条件を有する一人一人の多様性が尊重される地域共生社会のあり方について一緒に考えられればと思います。
プロフィール:宮城県出身。専門は、特別支援教育、重複障害教育、教育心理学。東北大学大学院教育学研究科総合教育科学専攻博士課程後期修了、2006年、宇都宮大学教育学部に着任。博士(教育学)(2007年)
面接授業科目:重い障害がある人への教育的対応(2009年)、障害の重い子どもの教育のあり方(2011年・2017年・2023年)
特別ゼミのテーマ:特別支援教育と共生社会―教育的係わり合いからの検討―(2024年、2025年)
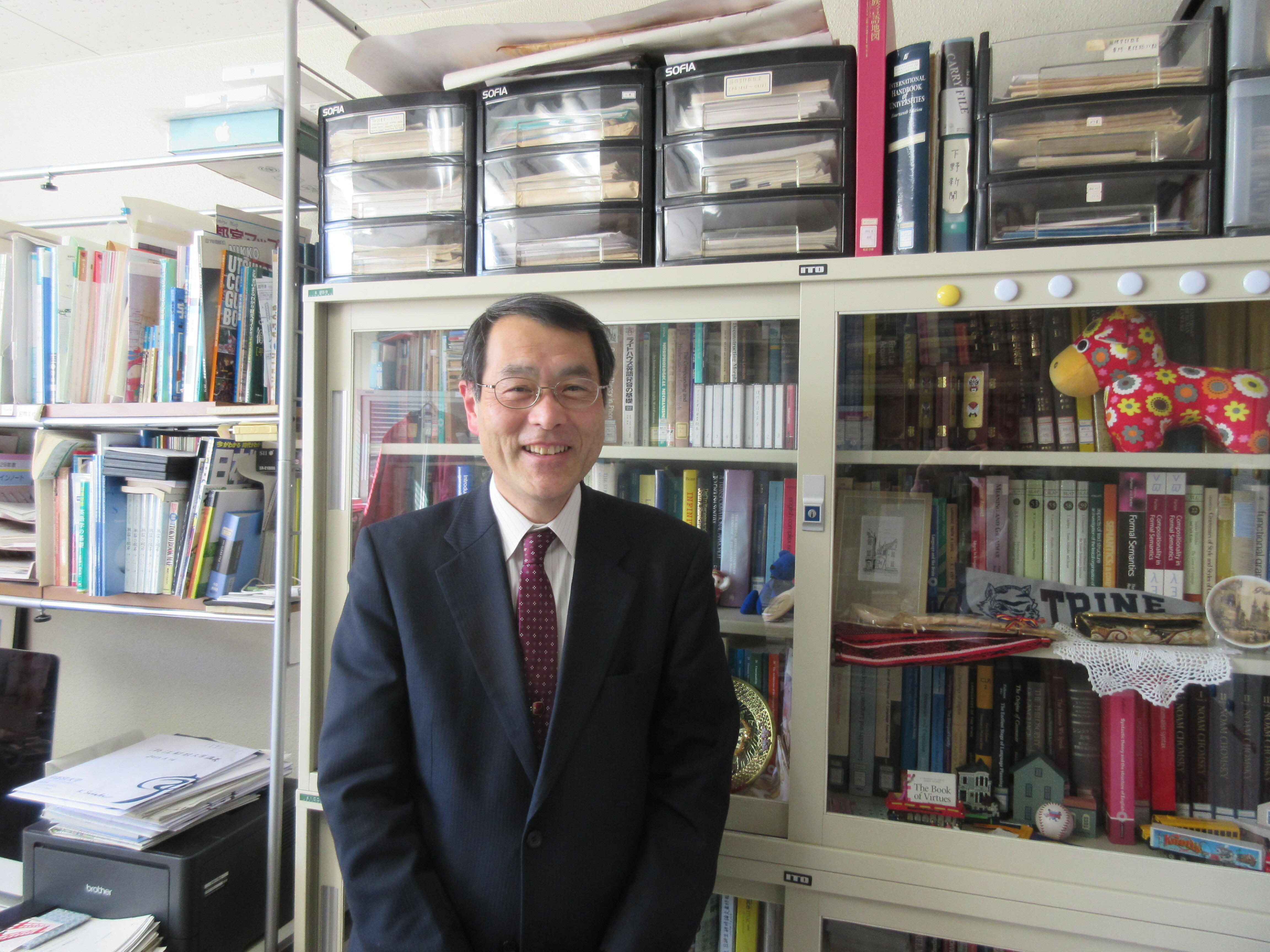
佐々木 一隆
客員教員/宇都宮大学名誉教授/専門分野:英語学・言語学
学生時代より英語の構造と機能を中心に研究してきました。具体的には英語の受動文や関係節の構造と意味、英語名詞句の内部構造と統語的分布などに焦点をあて、英語の構造には普遍性がある一方で多様性が顕著に見られる点を記述し、それがなぜかを言語獲得や機能の視点から解明してきました。また、英語を日本語などと比較する研究も行い、コミュニケーションのための英文法構築も進めています。こうした研究に基づき、宇都宮大学では言語学、言語比較論、Directed English Writing、卒業研究などを、同大学院では言語普遍性と英文法研究や特別研究(修論・博論指導)を担当しています。卒業論文、修士論文、博士論文の指導を重視し、これまでに多くの卒業生・修了生を育ててきました。
プロフィール:東京都出身。東京学芸大学大学院教育学研究科英語教育専攻(英語学講座)修士課程修了。1987年宇都宮大学教養部に着任し、1994年10月に同大学国際学部に異動。教育学修士(1983年)。
面接授業科目:時事英語II(2002年)、時事英語III(2004年)、言語研究への招待(2005年)、日本語から見る英語の読解と作文(2012年)、ことばと文化の関係について考える(2017年)、比較の視点から英語を学ぶ(2022年)、ことばの多様性と普遍性を探る(2023年)
特別ゼミのテーマ:言語・文化・比較研究(2022年)、日本語を世界の諸言語と比較する(2023年)、言語学講読:ChomskyとLakoffを読む(2024年)、ことばの不思議を考える(2024年)、日本語の文法について考える(2025年)

佐藤 隆之介
客員教員/宇都宮大学准教授/専門分野:生産加工学
ものを作るために素材を切ったり、削ったり、磨いたりする技術を専門としています。中でも砥粒と呼ばれる小さくて硬い粒を使った研削・研磨加工技術を主な研究テーマとしています。
プロフィール:北海道出身。18歳で宇都宮大学工学部に入学し、以来三十数余年を宇都宮大学で過ごしています。
面接授業科目:ものづくりの歴史と機械加工技術(2022年)
特別ゼミのテーマ:切削加工のメカニズム(2025年)

清水 奈名子
客員教員/宇都宮大学教授/専門分野:国際関係論
研究テーマは、戦争をはじめとする武力紛争において、なぜ一般市民が多く犠牲になるのか、どうすれば人々を保護することができるのかという問題について、国連の安全保障体制を中心に研究してきました。また2011年3月11日に発生した東日本大震災と原発事故を受けて、福島県内外にひろがる被害を調査し、被害を受けた人々の人権が果たして保障されているのかについても、研究を行っています。
プロフィール:東京都出身。専門は国際関係論。国連安全保障体制における文民の保護について研究しているほか、原発事故後の栃木県の被害についても調査を続けている。博士(教養)
面接授業科目:一般市民と戦争 その歴史と課題(2012年)戦争と平和をめぐる諸問題(2018年)
特別ゼミのテーマ:戦争と平和の歴史から学ぶ(2022年)、平和のための国際機構の歴史を学ぶ(2023年)、市民の目から見た戦争と和解(2024年)、市民が伝える戦争の記憶と体験(2025年)
下郷 大輔
客員教員/作新学院大学講師/専門分野:犯罪心理学・家族心理学
精神科クリニックや総合病院の心療内科、刑務所で心理師として臨床活動を行ってきました。刑務所での臨床実践が一番長く、受刑者の再犯防止と家族関係について研究を行っています。今後は社会内で受刑者の再犯防止を支える臨床や研究を行いたいと考えています。皆様との交流の中で、よく耳にする一方で扱いづらい『犯罪』という事象について、一緒に考えていければと思います。
プロフィール:広島県出身。専門は司法・犯罪心理学。修士(心理学)。
面接授業科目:司法・犯罪心理学概論(2023年)
特別ゼミ:家族関係を通して自分を考える(2023年・2024年)
二瓶 賢一
客員教員/宇都宮大学教授/専門分野:天然物有機化学
天然物はさまざま生物が作り出す化合物のことで、私たちの身近に存在します。例えば、パンの中にも、テーブルの中にも、それらは含まれています。化学の概念が希薄だった時代から,天然物は文化に溶け込み、歴史を紡いできました。そのような天然物とそれを取り巻く世界の面白さをできるだけ分かりやすくお伝えしたいと思っています。
プロフィール:福島県生まれ。所属学会は、日本農芸化学会、有機合成化学協会。博士(農学) 。
面接授業科目:旅する有機化学(2020年)。旅する天然有機化合物(2025年)
特別ゼミのテーマ:香りの化学(2025年)

横田 隆史
客員教員/宇都宮大学教授/専門分野:計算機工学
大学院修士課程修了後に電機メーカーに就職し、研究所でコンピュータの「つくり」に係わる研究を行ってきました。
1980年代後半に「AIチップ」を、1990年代中盤にかけて新方式の並列コンピュータを(新情報処理開発機構に出向)、その後2000年までコンピュータ技術の産業応用を研究してきました。
2001年に宇都宮大学工学部に着任し、引き続きコンピュータの基本部分の研究をしています。
プロフィール:埼玉県出身。専門は計算機アーキテクチャ。所属学会:情報処理学会、電子情報通信学会、IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers, 米国)、ACM(Association for Computing Machinery, 米国)。博士(工学)。
面接授業科目:情報科学とその応用(2003年)、実践オペレーティングシステム(2017年)
特別ゼミのテーマ:パソコンOSの裏側を覗いてみる(2024年)コンピュータの高速化~人間くさい裏技を知る(2024年)、パソコンOSの裏側を見てみる(2025年)


