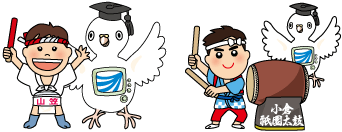所長ご挨拶
「ノーベル賞に触れて考える"学びの意味"」
新年明けましておめでとうございます。
本年が皆さまにとって健やかで、新しい学びや出会いに恵まれる一年となりますよう、心よりお祈り申し上げます。
さて、2025年の日本の科学界には、とても明るい話題がありました。日本人研究者がノーベル生理学・医学賞とノーベル化学賞の二つを受賞したのです。前年の被団協による平和賞に続き、二年連続で日本が世界から評価され、私自身も大きな励ましをいただきました。特に、ニュースの中で「金属錯体」という専門用語が取り上げられたのを耳にし、長年この分野に関わってきた者として、思わず嬉しくなりました。
生理学・医学賞を受賞された坂口志文先生は、免疫の働きを調整する「制御性T細胞(Treg)」を発見し、その機能を明らかにされました。免疫は強いほど良いと思われがちですが、暴走すれば自分自身を攻撃してしまいます。Tregは、いわば免疫の"ブレーキ役"。攻撃と抑制のバランスが、人間の健康を支えているのです。このTregは人気マンガ・人気アニメ『はたらく細胞』にも登場し、若い世代の科学理解にも貢献しています。
一方、化学賞を受賞した北川進先生の研究は、錯体化学が専門の私には特に身近なものです。北川先生は金属イオンと有機物を組み合わせ、ジャングルジムのような三次元構造を持つ「多孔性金属錯体(Porous Coordination Polymer:PCP)」を創出しました。同様の研究を進めたアメリカのYaghi博士は、これを「有機金属構造体(Metal Organic Framework:MOF)」と呼びました。その後、国際的にはMOFが広く使われ、今回のノーベル賞発表でもMOFが採用されています。北川先生は、受賞連絡の際に「MOFでよいか」と確認があったという逸話を紹介されました。名前は、研究分野の発展そのものを左右する、大変重要な要素なのだと改めて感じます。
昨年10月と11月に北川先生の講演を拝聴し、その中で語られた「無用の用」という言葉が印象に残っています。MOFは何に使うのか当初は未知数でしたが、微細な空孔が特定の分子を吸着し、選択し、運ぶ機能を持つことが明らかになり、ガス吸蔵、触媒、CO₂回収、医療応用など、応用範囲が一気に広がりました。資源の乏しい国でも空気から何かを生み出せる「夢の材料」と言われる所以です。まるで"霞を食べて生きる仙人"が現代科学で再現されるかのようです。
今回の二つのノーベル賞は、分野こそ異なりますが、「見えない世界の理解が未来をひらく」という科学の精神を示しているように感じます。学びは年齢とも過去とも関係ありません。いつからでも、どこからでも始められます。放送大学での学びが、皆さまの生活や視点を広げるきっかけになれば幸いです。
本年もどうぞよろしくお願い致します。

令和8年1月1日 福岡学習センター所長
久枝 良雄