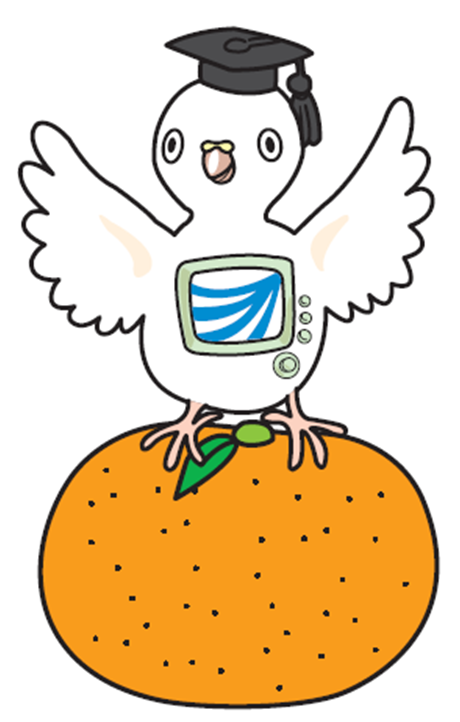教員紹介
愛媛学習センターでは、所長と8名の客員教員が皆さんの学習をサポートします。学生の抱えている修学上の様々な問題についてお答えする学習相談や、学生・一般の方向けの「公開講演会」を担当しています。お気軽にご参加ください。なお、「学習相談」の日時は変更されることがありますので、相談を希望される方は、事前に事務室窓口にお問い合わせください。特別講演会・卒業ガイダンス・大学院修士全科生入学希望者ガイダンスを開催いたします!

吉田 正広(よしだ まさひろ)
放送大学愛媛学習センター所長
専門分野:イギリス近現代史
自己紹介:私は、神奈川県横浜市出身で、1996年4月に愛媛大学法文学部に職を得て、松山の地に移り住みました。以来、26年間愛媛大学で西洋史担当教員を務め、2022年3月末に定年退職を迎えました。1年間のブランクを経て、愛媛学習センターにお世話になります。私の専門分野はイギリス近現代史です。今は第一次世界大戦の戦死者の追悼や戦争記念碑の問題を「悲しみの場」として、また、地域社会の問題として研究しています。法文学部時代に「四国遍路と世界の巡礼」研究に関わってたどり着いたテーマです。若い頃は1930年代イギリスの景気浮揚策としての「低金利政策」(「アベノミクス」に似ています)を様々な角度から調べ、イギリス福祉国家の成立と教会との関係についても考えてきました。明治以降の日本が近代化の中で常にモデルとしてきたイギリスについて、皆さんと一緒に学べればと思っております。
メッセージ:愛媛学習センターに集う学生の皆さんが少しでも良い環境で学ぶことができるよう、教職員一丸となって努力して参ります。学習の進め方をはじめ、修学上の様々な相談に応じます。気軽にお声をかけてください。

一色 正晴(いっしき まさはる)
専門分野:情報工学
自己紹介:2024年度から放送大学の客員教員に就任いたしました。私の専門は情報工学で、特に画像処理や人工知能(AI)の技術を産業界へどのように応用できるかについて興味を持っております。これまでの研究で、農家の方が主観的に評価していた形状の等級を、AIを用いて評価する手法の提案などを行っています。この技術は、生産者の作業負担を軽減し、消費者にはより良い品質の商品を提供することに貢献することができます。
このようなシステムで用いられているAIは、人間の脳細胞を模擬したニューラルネットワークが基礎となっています。ニューラルネットワークは、あまり良い性能がでないなどの理由で長い「冬の時代」がありましたが、今から10年ほど前に、地道な研究と改良により多くの成果を上げ始めたことに大きな感銘を受けました。このことで、持続的な学びと基礎研究の重要性を実感し、これを教育にも活かせればと考えております。教育面では、基礎から応用まで段階的に理解を深められるように構成することを心がけています。また、皆さんが実際に手を動かし、実践的なスキルを身につけられるよう、実習を学習に取り入れています。
これからも技術革新が進む中で、皆さんと共に新しい問題に取り組み、解決策を見出すことで社会に貢献していきたいと考えています。情報工学の進歩がもたらす可能性は計り知れませんが、それを適切に理解し、使いこなすためには、しっかりとした学びが不可欠です。私は皆さん一人一人がそのポテンシャルを最大限に発揮できるよう支援していきたいと考えております。
メッセージ:放送大学での学びは、単なる知識習得にとどまらず、多様な経験や背景を持つ皆さんが集い、それぞれの知見を共有し合う豊かな体験が得られます。この相互作用が、新たな洞察や理解を促し、学びの深みを増します。日々進化する知識や技術の中で、私も皆さんとともに学んでいきたいと思います。

城戸 茂(きど しげる)
専門分野:教育学
自己紹介: 2021年度から客員教員に就任いたしました。私は、公立学校教員を20年間、教育委員会の指導主事を7年間、文部科学省教科調査官・総括研究官を4年間務め、学校現場や教育行政の経験を生かしながら大学での教員養成に取り組んでいます。専門は教育学で、現在、教員を目指す学部生のほか、小・中・高等学校の現職教員の方々と学部卒業生が共に学ぶ大学院教育学研究科(教職大学院)というところで、生徒指導や特別活動に関する講座を担当しています。これからの教育においては、自分の価値を認識するとともに、相手の価値を尊重し、多様な人々と協働しながら社会の変化に対応しつつ様々な課題に柔軟に対応していく資質や能力を、学校・家庭・地域が連携を図りながら育成していくことが求められています。こうした教育の在り方について、体験活動の側面からアプローチしていきたいと考えています。
メッセージ: これまで、何度か放送大学の講座でお話をさせていだく機会がありました。幅広い年齢層の方々が受講されていますが、年齢に関係なく、学ぶことに対する熱意を持たれた方が多く、共に学ぶことの楽しさを私の方が教えていただきました。学びに対する熱意と様々な経歴をもった幅広い年齢層の方々が集う放送大学の強みを生かしながら、豊かな学びの輪を広げていきましょう。

水口 啓吾(みなくち けいご)
専門分野:発達心理学、臨床心理学
自己紹介:2024年度から客員教員に就任いたしました、水口啓吾と申します。私は、心理学の中でも、特に、発達心理学と臨床心理学を専門に研究をしています。現在は、愛媛大学教育学部(教育学研究科)に所属をしており、保育士や教師を志す学部生の皆さん、臨床心理士や公認心理師を志す大学院生の皆さんに、発達心理学と臨床心理学に関する理論とスキルをお伝えしています。心理学の楽しさや魅力について、たくさんの方に知っていただけたら幸いです。これから、どうぞよろしくお願いいたします。
メッセージ:「知りたい」「学びたい」という思いは、まだ知らない新しい世界の扉を開くきっかけを我々に与えてくれます。そしてそれは同時に、新しい自分と出会う始まりでもあると思います。皆さんにとって、放送大学での"学び"や"出会い"が、そのような場所や機会になっていただければ幸いです。私自身もこれからその輪の中に仲間として携わらせていただけることが嬉しく、楽しみです。これから、どうぞよろしくお願いいたします。
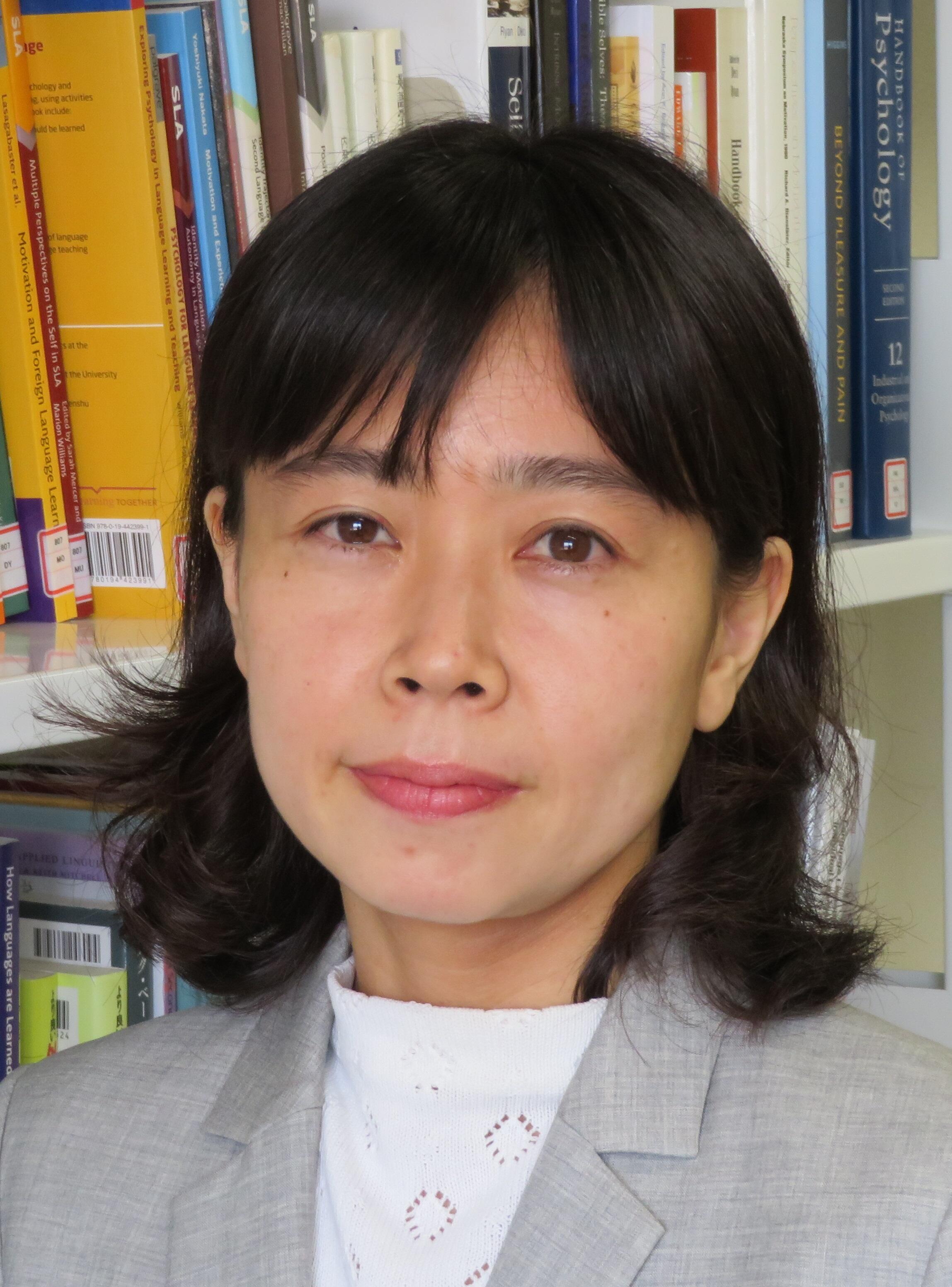
高橋 千佳(たかはし ちか)
専門分野:第二言語習得理論
自己紹介:2021年度より客員教員に就任いたしました。専門は第二言語習得理論で、特に、第二言語、つまり、外国語を習得する際に学習者間の違いを引き起こす心理的要因に興味があります。この分野に興味を持ったきっかけは、NHKのテレビやラジオ英語講座番組制作の仕事をしていた時に、講座で何年も学習を継続する人がいる一方、多くの人はなかなか学習が続かないのはなぜか、疑問に思ったことでした。そして、学習の継続にはどうも「動機づけ」といわれるものが関わっているようだということがわかりました。高い習熟度に達するのに長い時間がかかる外国語学習では、この「継続」という要素が非常に重要です。ただ、学んでいる外国語を使う機会があまりない環境で、特に強制力もないような場合、その継続はなかなか難しいとも思います。動機づけをはじめとして、学習を継続して高い習熟度に達する手助けとなる鍵をいろいろな角度から探しているところです。
メッセージ:外国語の習得は、簡単でないからこそやりがいもあり、学習の成果をコミュニケーションという場で実感することもでき、長い期間取り組む中で学習が楽しいと感じられるのではないかと考えています。出身地の愛媛で、皆さんと一緒に外国語の習得について様々な観点から考察していけることを楽しみにしています。
岡田 陽介(おかだ ようすけ)
自己紹介:2025年度より客員教員に就任しました岡田陽介です。30歳手前までは関東地方で過ごしていましたが、2010年9月から愛媛大学法文学部に勤務しています。放送大学では、これまでは2021年に一度だけ面接授業を担当しました。私の専門は法律学、その中でも商法という分野です。研究テーマの中心は株式会社をめぐる法ルールのあり方ですが、他にも運送や保険といった商取引に関する法ルールについても研究しています。商法という学問分野はその領域がたいへん幅広く、そのため商法を学んでいると、経済社会のものの見方・考え方などが自然に身についたりもします。また、研究の手法もさまざまで、最高裁判所などの判例の研究のようなガチガチの法解釈をしたと思えば、現代の経済社会における望ましい法ルールのあり方を考えて提唱したりもします。会社法についての最近の研究を紹介すると、前者については会社分割に関する判例や敵対的企業買収に関する判例を研究し、後者については企業統制システムやグループ企業に関する法ルールのあり方をテーマに研究をしました。株式会社といっても、上場企業のような大規模な会社だけではありません。小規模な同族企業についても研究の対象なので、あまり想像がつかないかもしれませんが、人間臭さがにじみ出るようなドロドロとした事件についての判例が多いのもこの分野の特徴です。このように、さまざまなテーマを、幅広く、いろいろな視点・観点から研究するように努めています。
メッセージ:みなさんとは、商法に限らず、法律学全般について、ともに学び、考えていけたらと思います。「学習相談」の時間に、気軽にお越しください。これからどうぞよろしくお願いいたします。
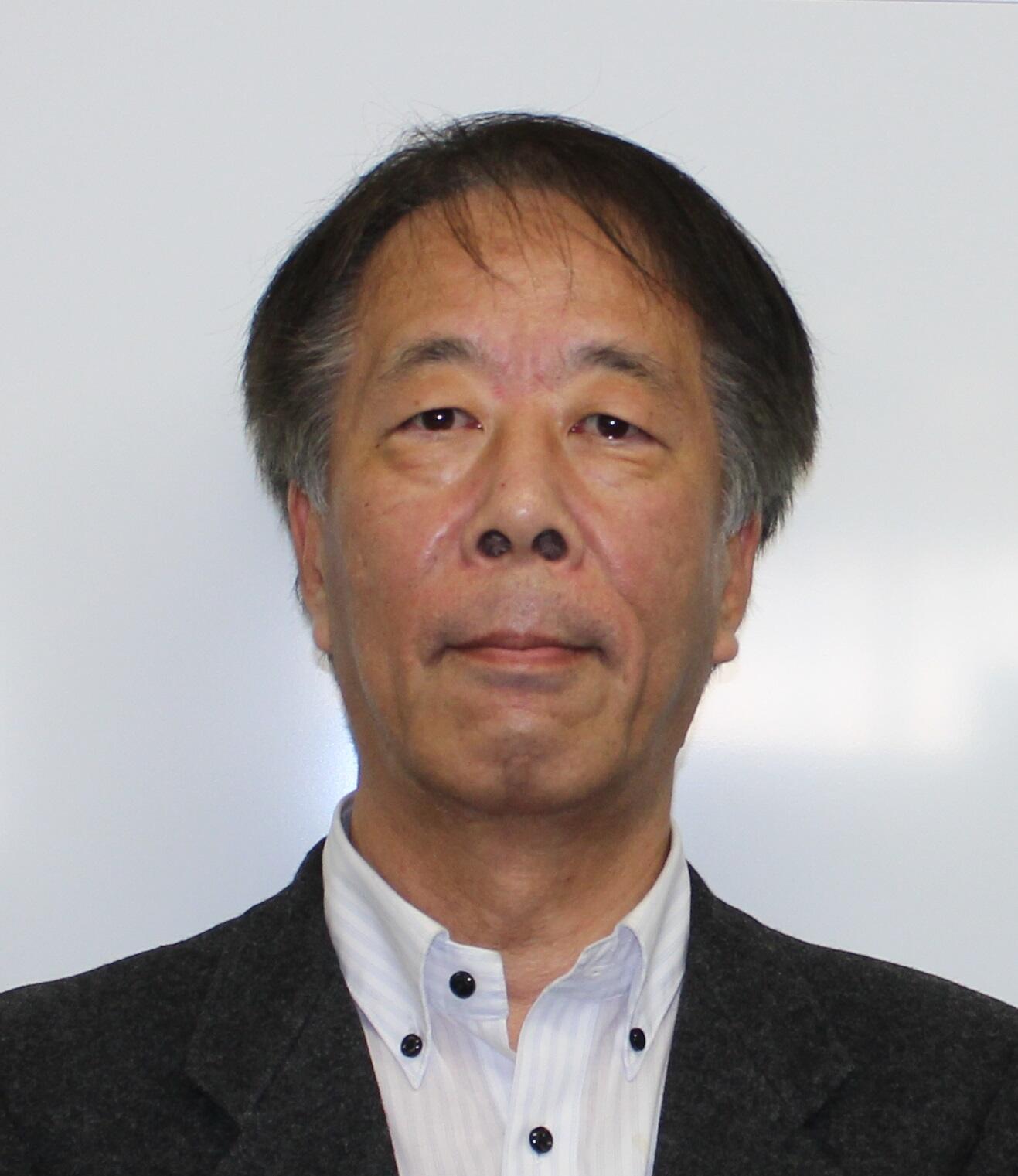
松枝 直人(まつえ なおと)
専門分野: 環境保全学 無機・物理化学
自己紹介: 2021年度から客員教員に就任いたしました。農学部の環境保全学コースに所属しています。物理化学から土壌学、粘土鉱物学を経て、現在は、途上国貧困層の飲料水の浄化に取り組んでいます。日本では蛇口を捻るだけで安全・安心・安価な水が出てきます。一方、途上国では水不足に加え、毎年およそ100万人が飲料水の汚染によって命を落としており、そのほとんどが乳幼児であるとされています。ヒ素・水銀・鉛などに加え、糞便性大腸菌などの病原微生物による汚染が広範かつ深刻です。日本などの先進国では科学技術とインフラによってこれら汚染物は容易に除去できますが、途上国貧困層の人々は、それらの恩恵に与ることができていません。そこで、物理化学・土壌学・粘土鉱物学の知識を活用して、家庭で子供でも使える安価な浄水ツールの開発に取り組んでいます。放送大学では、「化学」や「土」、「水」、「浄水技術」についてご紹介させて頂く予定です。
メッセージ: 私などよりもはるかに人生経験豊富な方々のお役に立てるかどうか、たいへん不安に思っています。他方で、自身の研究テーマを様々な分野、立場、経歴の方々にご紹介することで、全く新しいものの見方ができたり、思いがけないヒントを得たりするのではないか、との期待もあります。いろいろと学ばせて頂ければと思います。

森本 千恵(もりもと ちえ)
専門分野:生化学、基礎栄養学
自己紹介:2024年度より客員教授に就任しました森本千恵です。2014年4月から5年間、放送大学の客員教員として勤めておりましたので、今回は2度目になります。当時は出身地である松山に戻って現職に就いて2年経った頃で、放送大学の学生さんたちとふれあうことでたくさんの刺激をいただいておりました。公開講演会では様々な年齢層の方たちが熱心に聴講され、質疑応答では鋭い質問を受けたこともあり、その熱意に押されて身の引き締まる思いでした。再びその機会に恵まれましたことを大変幸運に感じております。
これまで愛媛大学医学部生化学教室、広島県にある安田女子大学薬学部に在籍し、12年前に松山に戻って、現在は松山東雲短期大学で栄養士の養成に携わっております。専門は生化学、基礎栄養学です。身体の中で栄養素がどのように変化してどのような働きをしているのかについて講義や実験を通してできるだけわかりやすく解説しようと心がけています。「生化学」の分野といってもこれまで在籍していた医学部および薬学部と栄養士養成施設とでは、視点が異なり面白いなと感じています。極端にいえば医学部では「病気」を意識し、薬学部では「薬のターゲット」を意識し、栄養士養成課程では「健康」を意識しています。その中で、「食べる」ということがとても大切であり、生活習慣病をはじめ様々な病気に罹らないための第一歩は「健全な食生活を送る」ということであると強く認識しております。
80年以上生きることが珍しくなくなった現在、自分のことは自分でできる時間をできるだけ長くもつことが課題となっています。これまでの経験を踏まえて、公開講演会では「新・健康に生きる」というテーマで前回からバージョンアップさせて講演していく予定です。
出勤日は基本的に毎週土曜日の午後です。前回のときには複数の先生方が同日の勤務でしたが、今回は一人ですので少し寂しく感じております。いつでも話しに来ていただければと思っております。
メッセージ:学びはいつからでも始められます。そして、個々が主体的にそれぞれにあった方法で、生涯にわたって楽しく学び続けることが大事です。放送大学での新たな学びや様々な世代の人たちとの交流を通して、今後の人生の可能性と素晴らしさを、身をもって実感することができるのではないでしょうか。
これからよろしくお願いいたします。

西嶋 真理子(にしじま まりこ)
専門分野:公衆衛生看護学
自己紹介:2023年度から客員教授に就任しました西嶋真理子です。専門は公衆衛生看護学です。愛媛県の大洲保健所、宇和島保健所、伊予保健所で計6年間、保健師として働き、現在は、愛媛大学大学院医学系研究科看護学専攻に勤務して、20年近くになります。
保健師学生の教育を担当する傍ら、発達障害のある子どもを育てている親に対する支援やその研究に取り組んでいます。子どもに発達障害の特性が見られる場合、親は子どもの様々な症状にどう対応したら良いか悩まれます。けれども発達障害は、個性の延長線上にあるとも言えるため、日常生活に様々な支障をきたしていても、その理由を理解することが難しく、どうしてできないのかと思い、ついつい子どもに対して不適切な対応になりがちです。そうなると、子どもはますますうまくいかないことが多くなり、親はさらにイライラしていくという悪循環に陥ります。そのような袋小路に陥っているときに出会ったのが、オーストラリアで生まれた「前向き子育てプログラム(Positive Parenting Program; Triple P)」です。
子育ての技術を分かりやすく、前向きに伝えるこの方法は、発達障害等の障害の有無にかかわらず、すべての子どもを育てている親が使える技術です。親子の建設的な関係を育み、子育てをぐっと楽にすると同時に子どもの持っている能力を伸ばすことができると思います。育児不安のある多くの親や周囲の大人、誰もが身近で学ぶことができれば、どんなに素晴らしいだろうと思っています。
メッセージ:放送大学では様々なご経験を積まれた学生さんや先生方と出会えるのを楽しみにしています。Triple Pは、育児だけでなく、家庭や職場の大人同士の人間関係にも応用できると感じています。皆様と一緒により深く学び合えると、きっと新しい発見があると思います。