教員紹介
東京文京学習センターでは、所長以下、客員教員11名の計12名の教員が勤務しています。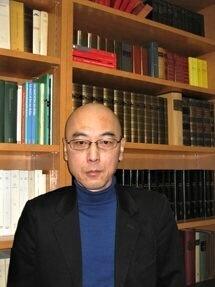
熊野 純彦(くまの すみひこ)
学習センター所長/教授〔哲学、倫理学〕
2023年4月より東京文京学習センターの所長を務めております。元来の専門は哲学・倫理学です。ただ私自身は、一つの問題を自分で考え抜いてゆくタイプの研究者ではなく、むしろ様々なテクストを読み解き、作者との対話を自分の中で重ねながら、その結果を翻訳や著書の形で発表してきました。対話の相手として選んできたのは、主に近現代のドイツ系の哲学者、たとえばカントやヘーゲル、またカッシーラーやハイデガー、現代フランスの哲学者、たとえばベルクソンやサルトル、メルロ=ポンティ、レヴィナスといった人々です。他にもマルクスや近世日本の思想家(本居宣長など)、現代日本の文学者(三島由紀夫など)も対話の相手としています。そのような経験を学生の皆さんとの交流に少しでも活かし、学習することの喜びを共有したいと祈念しています。

安藤 宏(あんどう ひろし)
客員教授〔日本近代文学〕
私の専門は日本の近代文学です。明治~昭和期にいたる、小説の文体、表現史に関心があり、一般書としては『日本近代小説史』(中公選書)、『「私」をつくるー近 代小説の試み』(岩波新書)などがあります。前者は以前の放送大学の授業科目の一 部を書き直したものです。特に力を入れてきたのは太宰治の研究で、2021年に専 門書として、『太宰治論』(東京大学出版会)を出しました。あと、目黒区駒場の日本近代文学館の専務理事を務めてますので、館の企画で、みなさんとお会いする機会 もあろうかと思います。2024年春に東京大学を定年退職し、執筆活動を続けてます。どうぞよろしくお願い申し上げます。

池田 嘉郎(いけだ よしろう)
客員教授〔近現代ロシア史〕
私の専門は近現代ロシア史研究です。ロシアでは1905年、1917年、1991年と3度大きな体制変革の機会がありましたが、基本的な統治の構造はこれらの転換点を超えて継承されました。それは第一に統治者が法の上に立つという政治文化であり、第二に住民を団体に編成して統治を行なうという支配の仕組みです。この二つの契機がいかにして再生産されているのかを明らかにすることが、私の主題です。言い換えれば、権力をめぐるロシアの政治文化を明らかにしたいのです。これまで第一次世界大戦からロシア革命を経てスターリン時代にいたる政治史を研究してきました。その一方で、研究を進めるにつれて、権力の問題を明らかにするためには人の心の奥へと降りていく必要があるとの考えをもつにいたりました。そのため現在は文学研究にも大きな関心をもっています。

小田部 胤久(おたべ たねひさ)
客員教授〔美学〕
私は主に18世紀中頃から19世紀初めにかけてのドイツ語圏の美学理論(その代表的論者はカントです)を研究しています。学問としての美学も、今日私たちが用いる意味における芸術という術語も、この時代に成立しました。両者の成立過程を、古典古代から現代にいたる西洋の思想史の文脈のうちに解明する作業に携わっています。と同時に、美学や芸術が近代日本に移入され定着する過程にも関心を寄せています。美学という語の用例として、『広辞苑』では「引き際の美学」が、『日本国語大辞典』では「生活の美学」(石川淳)が挙げられていますが、美学を生活に即して捉える考え方は日本に特有のものです。美学のさまざまな可能性について、皆さんと議論できれば幸いです。と同時に、「引き際」を忘れないよう自戒せねばなりません。
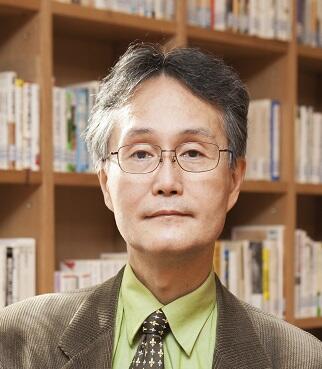
小野塚 知二(おのづか ともじ)
客員教授〔歴史学・経済学〕
わたくしの専門は経済学と歴史学の境界の経済史という研究領域です。20代から研究を続けているのは、イギリス近代(≒19世紀)と現代(≒20世紀)の労務管理・労使関係の歴史です。近現代産業社会で、最も多くの人が関わる人間関係が労務管理と労使関係ですが、その中でも集団的な労使関係・労務管理が生成し変容してきたさまを調べています。このほかに、第一次世界大戦の原因とその民衆的な要因、イギリス食文化・食糧史(近代イギリスは料理がまずくなったが、なぜ飢えなかったか)、野良猫のいる社会といない社会(現在の世界には野良猫のいる日本やイタリアのような国と、野良猫がほぼ消滅してしまったイギリスやドイツのような国がありますが、野良猫はなぜ、どのようにして消滅したのか、そのことは何を物語っているのかという問題)、国際武器移転史、原料革命と温暖化問題・人口減少の関連などについても研究を進めています。

鈴木 泉(すずき いずみ)
客員教授〔哲学〕
専門は哲学です。スピノザを中心とした17世紀の西洋哲学とドゥルーズを中心とした現代フランス哲学を主たる素材としてものを考えて来ました。自前でものを考えることも大事ですが、少なくとも私の場合、自分の身の丈を越えて思考を羽ばたかせるという冒険に乗り出すためには、彗星のような哲学者や奇矯なことを考え抜いた風変わりな哲学者の助けが必要でした。ただし、特殊な術語によって構築される哲学的な思考の世界の意義を、一方で哲学史の文脈を出来るだけ踏まえると共に、他方で私たちの日常の経験や言葉に引き寄せ、一つ一つ確かめることを自分の仕事の柱の一つにして来ました。そういった来歴を活かし、日常の世界と過去の哲学史の森に片足ずつを据えつつ、学生の皆さんと哲学するという冒険の楽しさを共に出来たらいいと願っています。

永原 恵三(ながはら けいぞう)
客員教授〔音楽学、声楽〕
私は音楽学という学問分野と、声楽(西洋音楽)という実践分野とを専門にしています。音楽学では私たちが普段接している様々な音楽を、人間の豊かな営みと捉え、クラシックも民族音楽もポップスも全て同等に大切な音楽と考えます。音楽は感性の世界だけがすべてはなく、むしろ思考として緻密に構築された音の世界です。音楽について考えることは人間の思考にとって大切なことです。他方、私は声楽も音声生理学に基づいて研究し、歌曲演奏と合唱指導をしています。気持ちだけで音楽はできません。楽譜をしっかりと読み込み、それを身体の活動に落とし込むことで、演奏者と聴き手の間に強いつながりができると考えます。音楽は知的な活動です。思考としての音楽は,私たち一人ひとりの身体から生み出されます。身体を十分に使って音楽をしたり考えたりする醍醐味を分かち合いましょう。

細谷 浩史(ほそや ひろし)
客員教授〔原生生物学、細胞生物学〕
私達ヒトの体は数十兆個の「細胞」でできています。受精時は「1個」の細胞(卵)なのに、2個、4個と正確に分裂が進行していくメカニズムの全貌は今もって不明です。私は、ヒト子宮がん細胞(HeLa 細胞)やミドリゾウリムシ(単細胞の原生生物)を実験材料に、細胞の分裂機構解明を目指して研究を行っています。ミドリゾウリムシの体内には、クロレラに類似の共生藻が数百個共生しています。なぜ光合成を行える藻類が、行えない単細胞生物の中に、しかも数限定で共生しているのだろうか。なぜ数十、数千個ではなく数百個なのだろうか。藻類の分裂を制御しているメカニズムは何か?興味の種はつきません。皆様に、躍進する生命科学研究の一端をご紹介できたら幸いです。

丸山 純一(まるやま じゅんいち)
客員教授〔心理学〕
私の専門の心理学には実に多くの分野があり、著名な研究者も多数います。私が若い頃に興味を持ったものを挙げるだけでもその多様性が分かると思います。高校では精神医学者島崎敏樹、大学の教養課程ではモラトリアム人間論の小此木啓吾の精神分析、河合隼雄のユング派心理学、荻野恒一の現存在分析関係の本が印象に残っています。理学部で動物行動学を学んでいた時にアロンソンのThe social animalを偶然手にして社会心理学を志し、大学卒業後に心理学科に学士入学しましたが、ピアジェの認知発達、認知心理学、パーソナリティなどについても興味を持ちました。また、大学の先輩とストレスチェックを作り、美術大学に就職してからは視知覚についても学びを深めました。心理学には皆さんも興味を引かれる分野がきっとあるはずです。一緒に学びましょう。

森 義仁(もり よしひと)
客員教授〔化学〕
物理と化学を合わせて理化学と呼ぶことがあります。理化学の源流を実験と捉えるなら、自らの手で実験に取り組み、ああでもないこうでもないと、理化学を楽しんでみたいです。約100年前に我が国で出版された、少年少女に向けた在宅実験を勧める書「容易にできる理化学実験」には、「百見は一試に如かず」の精神が書かれてあります。百回見るぐらいなら一回は自分の手を動かしてみようというわけです。それも自宅での実験ですから道具を探さないといけないし、条件の検討が必要となります。その経緯には工夫や考案が生まれます。その驚きこそがさらに気持ちを掻き立てるというわけです。「驚きは知識欲」とはこのことかなと思います。それではみなさんご一緒にいかがでしょうか。

頼住 光子(よりずみ みつこ)
客員教授〔日本倫理思想史、仏教思想〕
私の専門は、日本倫理思想史、仏教思想です。私は、これまで、道元や法然、親鸞を中心として、日本仏教にかかわる諸テクストをできる限り丁寧に読み解き、そこから日本仏教の人間観や世界観を浮き彫りにしようと取り組んで参りました。それらの中には、現代の私たちのものの見方を根底から支えているものもあり、また、現代の私たちのものの見方とは大きく異なるが故に、私たちを揺さぶり、問を投げかけることを通じて、新たな思想の形成と価値の創造へ導いてくれるものもあります。 私自身、仏教教義に関わるテクストだけではなく、仏教説話や謡曲など仏教文化、さらには、神話や近代日本思想も含め、日本思想に関わる多様なテクストを対象として研究を進めておりますので、幅広く学習上の相談に応じて参りたいと思っております。

小又 志郎(こまた しろう)
客員准教授〔物理学〕
物理学、特に素粒子論、場の理論、数理物理学の分野で研究を進めています。この世界の究極の構成要素は何か、それを支配する法則は何か、ということは古代から探究されてきた問題であり、素粒子に限らず多様なスケールの物理で問われるものです。また、そのような問題に取り組むために使われる数学的手法も、それ自体として多くの面白い問題を提供し、数理物理学として活発に研究が行われています。 難解そうに見える物理や数学ですが、基礎から一歩一歩着実に進んでいくことで理解を深めることができ、少しでも理解が進んだときの喜びは格別です。 面接授業、自主ゼミ、学習相談などの機会に、ご一緒に勉強していきましょう。


